〒289-1116 千葉県八街市中央10-8 JR八街駅北口 八街市役所斜め前
営業時間 | 8:45~17:15 |
|---|
定休日 | 土日祝日 |
|---|
交通事故 解決に向けて
交通事故の損害賠償責任

交通事故では多くの場合に加害者側に損害賠償責任が発生し、さらに概ね任意自動車保険にも加入していますので、損害賠償責任の有無が問題になることはそれ程多くないように思われます。
しかし、被害者・加害者双方が任意自動車保険に加入していないような場合には、損害賠償責任の有無や損害賠償責任が誰に発生するのか等について問題になることが考えられます。
交通事故の損害賠償責任については、民法とその特別法である自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で定められています。
これらの法律で定める要件を満たしてはじめて加害者側に損害賠償責任が発生することになります。そして、加害者側で賠償責任保険(自賠責保険、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険など)に加入している場合には、保険から賠償金が支払われることになります。
ここでは、民法と自賠法で定めている要件等について記載します。
民法上の責任を負う人
① 加害者本人(民法709条)
民法709条が交通事故の損害賠償責任の基本となる条文です。民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
加害者に損害賠償責任が発生するための主な要件としては、①故意・過失、②責任能力、③権利侵害、④損害の発生、⑤因果関係(①によって④がもたらされたこと)が挙げられます。
これらのうち②以外の要件は、被害者側で主張・立証していく必要があります。
② 加害者の使用者(民法715条)
直接の加害者が、使用者である会社のために仕事をしていたときに交通事故を起こしてしまった場合には、一定の要件のもとで直接の加害者とは別に、会社(使用者)にも責任が発生することがあります。
使用者に損害賠償責任が発生するための主な要件としては、①加害者と会社との間に使用者・被用者の関係があること、②加害者が事業の執行につき、③第三者に不法行為(加害行為)を行ったことが挙げられます。
これらは被害者側で主張・立証していく必要があります。①〜③について立証した場合には、使用者が被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても損害が生じたであろうことを立証できない限り、賠償責任を負うことになります。
③ 加害者が複数の場合:共同不法行為(民法719条)
例えば、A車とB車が衝突したのちに(両方とも過失あり)、制御不能になったB車が歩行者に衝突して受傷させた場合、歩行者はA車、B車のどちらに対しても被った損害すべてについて賠償するように請求することができます。
B車が請求を受けた場合には、「A車との関係で自分の過失は7割だから7割分しか賠償しない」ということはできず、全額賠償する義務があります。 B車は全額賠償したあとで、A車に対してその過失分を求償することになります。
自賠法上の責任を負う人
① 運行供用者(自賠法3条)
交通事故の被害者救済を目的とする自賠法は、加害者側の責任を強化するために、第3条で民法の特則を定めています。主な特徴は下記のとおりです。
①「自己のために自動車を運行の用に供する者」=運行供用者という責任主体
運行供用者は、直接の加害者だけでなく、自動車の所有者など「自動車の運行を指示、制御すべき立場にある者」を言うとされています。
②他人の生命または身体に対する損害が対象
物損は対象外とされています(民法に基づいて請求します)。なお、被害者の方が「他人」に該当するか問題となることがあります。
③下記の3つの事由をすべて証明しない限り、責任が発生
・自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
・被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
・自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
② 保有者(自賠法2条3項)、運転者(自賠法2条4項)
自賠法では、運行供用者のほかに、「保有者」、「運転者」という主体を設けています。
「保有者」は、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう」と定義されており、運行供用者の中で自動車を使用する正当な権利を持っている人を言います。例えば、泥棒運転者は運行供用者には該当しますが、保有者には当たらないことになります。
「運転者」は、運行供用者に対する概念で、「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう」と定義されており、バスやトラックのドライバーなど会社のために運転をしている人が該当します。「運転者」は運行供用者ではありませんので、自賠法3条の責任ではなく、民法709条の責任を負うことになります。
この「保有者」と「運転者」が、自賠責保険の被保険者とされています(自賠法11条1項)。ひき逃げなどのように保有者が明らかではなかったり、加害者が泥棒運転者のように保有者には該当しない運行供用者の場合(さらに自動車の所有者に運行供用者責任も発生しない場合)には、自賠責保険の対象にはならず、政府保障事業の対象になります(自賠法72条1項)。
③ 加害者が複数の場合:共同不法行為
加害者が複数いて、複数の自賠責保険に請求できる場合には、自賠責保険の支払限度額が有責車両の台数分だけ増加します。
例えば、被害者の方がA車に同乗中に、B車と交差点で出会頭衝突し、双方に過失がある場合には、被害者の方の自賠責保険の傷害部分は、120万円×2台=240万円が支払限度額となります。


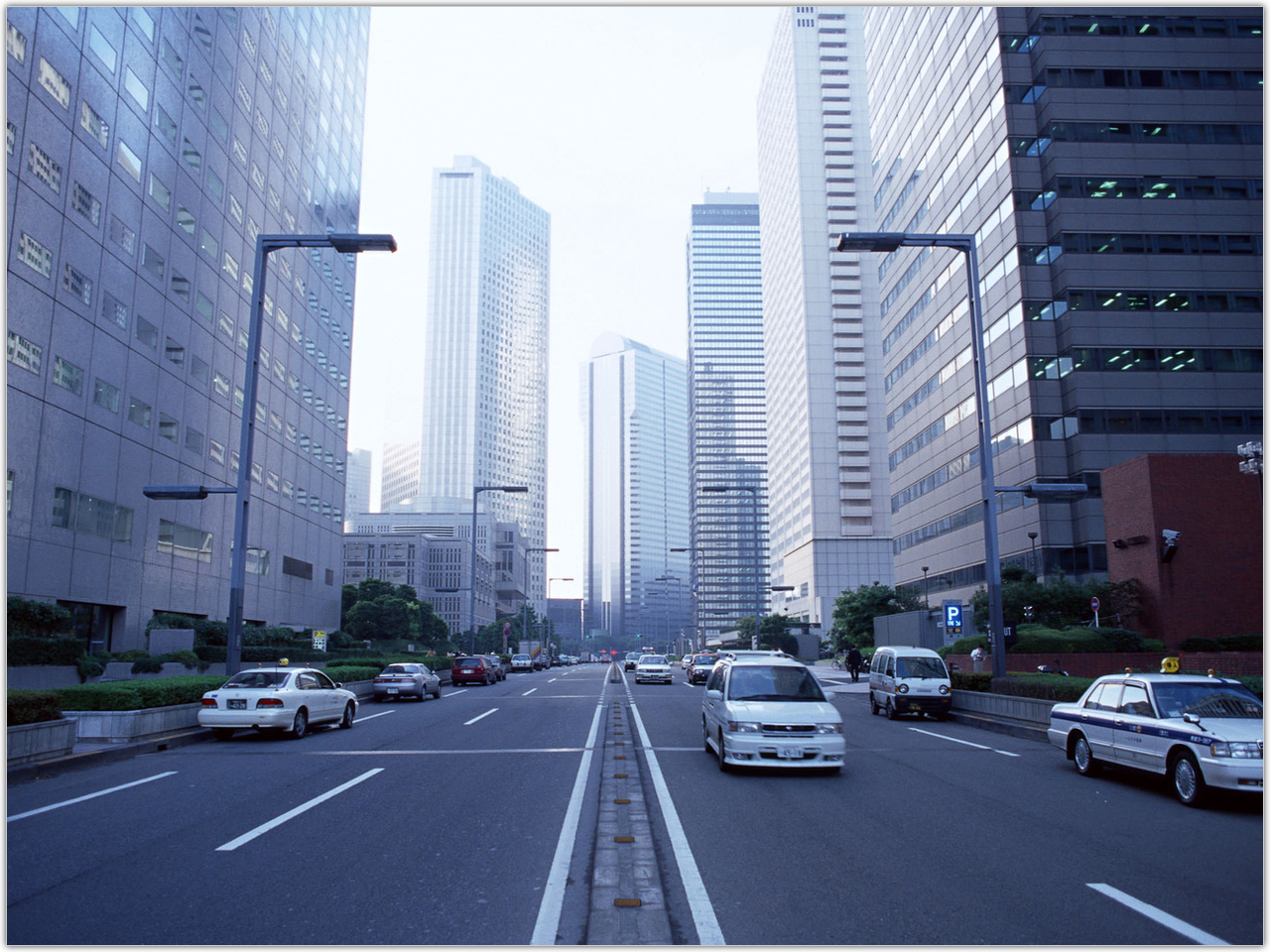
示談について
交通事故の損害賠償は、そのほとんどが示談、つまり加害者と被害者の話し合いにより行われます。そして、その話し合いがまとまると、内容を示談書にまとめ、双方が署名押印して、一通ずつ所持するのが普通です。
すんなりと加害者が賠償金を支払ってくれれば問題はありませんが、後日支払うと言いながらうやむやになってしまうこともあります。
このような場合、示談書を「公正証書」にしておけば、相手方が約束を破っても、新たに催告や裁判をすることなく、いきなり加害者の財産に強制執行をすることができます。
自賠責保険金の請求
自賠責保険はよく強制保険と言われるもので、法律により加入が義務付けられているものです。その他の特徴は以下の通りです。
- 保険の対象は、被害者のみで加害者側は補償されません。
- 被害者に対する「対人」に関する部分のみです。
- その他の損害を補うために加入するのが任意保険です。
- 自賠責保険の補償は被害者救済のための言わば最低限のもので、
保険料も低額なだけに、その補償される額も最低の基準となっております。 - 補償される内容は、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、葬儀費でそれ
ぞれ限度額の範囲内で支払われます。
必要な書類について
交通事故被害に遭うと、死亡、傷害(入院・通院)に伴い様々な書類をそろえて自賠責保険の請求を
することになります。主な必要書類は以下の通りです。
- 自賠責保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
交通事故解決・保険金請求のご依頼は

お問合せ・ご相談はこちら

親切・丁寧に対応します。
| 受付時間 | 9:00~17:00 |
|---|
| 定休日 | 土日祝日 |
|---|
会社設立、社会保険・労働保険の手続き、建設業許可他許認可申請、給与計算、会計記帳について、ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
会社設立 起業、独立開業に関するご相談
建設業許可他各種許認可申請 労務管理 会計記帳代行
給与計算 年末調整 その他 経営に関する煩わしいことは、行政書士・社会保険労務士『葵総合ブレーン本多事務所』にお任せください。
| 対応エリア | 八街市 千葉市中央区 千葉市若葉区 千葉市花見川区 千葉市美浜区 千葉市稲毛区 千葉市緑区 佐倉市 四街道市 八千代市 成田市 富里市 山武市 東金市 他上記の隣接市町村 その他 東京都23区内 |
|---|
お気軽にお問合せください
主な業務地域
八街市 千葉市中央区 千葉市若葉区 千葉市花見川区 千葉市美浜区 千葉市稲毛区 千葉市緑区 佐倉市 四街道市 八千代市 成田市 富里市 山武市 東金市 他上記の隣接市町村 その他 東京都23区内

